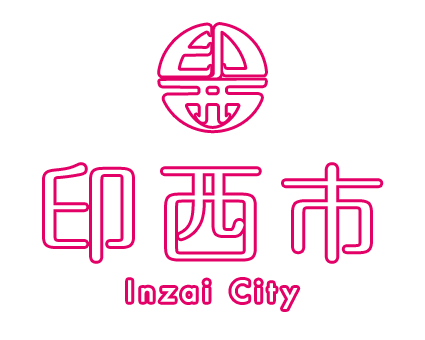[2014年10月1日]
ID:2595
小児の肺炎球菌感染症について
肺炎球菌は、乳幼児の上気道に感染し、化膿性髄膜炎、敗血症、肺炎などの重篤な全身感染症をおこすことがあります。この菌は、集団生活が始まるとほとんどの子どもが持っているといわれるもので、主に気道の分泌物により感染を起こします。これらの菌が何らかのきっかけで、肺炎や中耳炎、髄膜炎などの重い合併症を起こすことがあります。
肺炎球菌による化膿性髄膜炎の罹患率は、5歳未満人口10万対2.6~2.9人とされ、年間150人程度が発症していると推定されています。10%に難聴、精神の発達遅滞、四肢の麻痺、てんかんなどの後遺症を残すと言われており、また髄膜炎をきたした場合には約21%が予後不良とされています。 また、小さい子どもほど発症しやすく、特に0歳児でのリスクが高いとされています。
令和6年10月1日から小児用肺炎球菌ワクチン(沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン)が定期化されました
ワクチン接種により、肺炎球菌(ワクチンに含まれる種類のもの)が血液や髄液から検出されるような重篤な肺炎球菌感染症にかかるリスクを95%以上減らすことができると報告されています。
これまで、小児肺炎球菌ワクチンは13価(プレベナー13)および15価(バクニュバンス)を使用していましたが、令和6年10月1日より、原則として20価(プレベナー20:沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン)を使用することになりました。
新たに接種を開始する人は原則として、20価のワクチンで接種を開始してください。
これまで1回以上接種を済ませている人は、使用しているワクチンの種類によって、10月以降に使用するワクチンが異なりますので、下記の案内を参考にしてください。
(注意)接種回数や接種間隔は変更ありません。
新たに接種を開始する場合
20価のワクチンで接種を開始してください。
13価ワクチン(プレベナー13)で接種を開始している場合
令和6年10月1日より、13価ワクチン(プレベナー13)は、定期接種としての使用はできなくなりました。
すでに13価(プレベナー13)で接種を開始している人で、続きの接種を令和6年10月1日以降に受ける場合は、20価(プレベナー20)に切り替えて接種を受けてください。
15価ワクチン(バクニュバンス)で接種を開始している場合
すでに15価(バクニュバンス)で接種を開始している人は、続きの接種回数分を15価ワクチンで接種してください(原則)。
小児用肺炎球菌ワクチンの副反応について
注射部位の反応として、紅斑(66.2%)、硬結(60.9%)、腫脹(50.9%)、疼痛・圧痛(28.2%)などが報告されています。その他、食欲減退(31.4%)、発熱(71.3%)、発疹、注射部位のしこり、感冒(鼻咽頭炎など)などがみられます。
稀に報告される重い副反応としては、アナフィラキシー、けいれん、血小板減少性紫斑病等があります。
小児用肺炎球菌ワクチンの接種方法
下表ア~エは、接種を開始する月齢(年齢)によって接種回数が異なりますので、表で確認してください。
| 接種開始時期 | 接種回数 | 接種方法 |
|---|---|---|
ア.初回【生後2か月から7か月】 接種開始が生後2か月から7か月に至るまでの場合 | 初回 3回 | 〈初回〉 ・標準接種は、生後12か月までに27日以上の間隔をおいて3回接種 ★ただし、初回の2回目及び3回目の接種は、生後24か月に至るまでに接種すること それを超えた場合は接種しない(追加接種は実施可能) また、初回2回目の接種が生後12か月を超えた場合、初回3回目の接種は行わない |
ア. 【生後2か月から7か月】 初回の接種開始が生後2か月から7か月に至るまでの場合 | 追加 1回 | 〈追加〉 標準的には、生後12か月から15か月の間に、ア.初回接種終了後、60日以上かつ1歳を過ぎてから1回接種 |
イ.初回【生後7か月~12か月】 接種開始が生後7か月から12か月に至るまでの場合 | 初回 2回 | 〈初回〉 ・標準接種は、生後12か月までに27日以上の間隔をおいて2回接種。 ★初回の2回目の接種は、生後24か月に至るまでに接種すること。それを超えた場合は接種しない。(追加接種は実施可能) |
イ.【生後7か月~12か月】 初回の接種開始が生後7か月から12か月に至るまでの場合 | 追加 1回 | 〈追加〉 イ.初回接種終了後、60日以上の間隔をおいて、かつ1歳を過ぎてから1回接種 |
| ウ.接種開始が生後12か月に至った日の翌日から生後24月に至るまでの場合 | 2回 | 60日以上の間隔をおいて2回接種 |
エ.接種開始が生後24か月に至った日の翌日から生後60か月に至るまでの場合 | 1回 | 1回のみ接種 |
お問い合わせ
印西市役所 健康子ども部 健康増進課 感染症予防係(コスモスパレットⅡ 2階)電話: 0476-33‐3785(総合保健センター内) ファクス: 0476-46‐7770