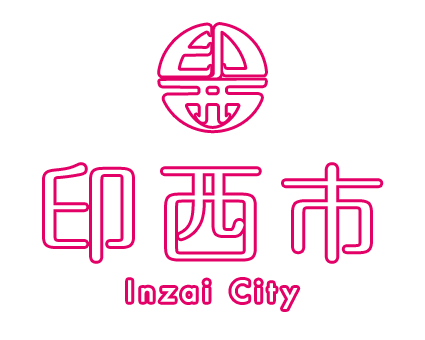[2021年9月1日]
ID:13048
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
印西伝統芸能フェスティバルとは
印西市内の無形民俗文化財に指定されている獅子舞・神楽が一堂に会し、舞を披露したものです。平成28年に印西市文化ホールで催されました。
動画は約12分にまとめられたダイジェスト版となっております。
誰もが文化に触れる良い機会となりますので是非ご覧ください!
閲覧は下記URLをクリック!
またフルバージョンのDVDは生涯学習課、大森図書館、小倉台図書館にて貸出しを行っております。
八幡神社の獅子舞
4月下旬に春の農作業の始まりの神事として行われます。おやじ(親父)、かか(母)、せな(若者)の3人の踊り手が力強く踊って、稲の籾蒔きの終わりを祝い、豊穣を祈ります。
鳥見神社の獅子舞
平岡地区では、稲の籾蒔き終了を祝う「オコト」という行事の日に、悪魔払いと豊作を祈願して獅子舞を奉納してきました。現在は鳥見神社の春の例大祭が行われる5月3日に奉納されます。
ジジ(親獅子)、セナ(若獅子)、カカ(雌獅子)によるいわゆる三匹獅子舞で、演目は「初の切」「二の切」「弓くぐりの舞」「ねむりの舞」「三角の舞」「みみず拾いの舞」「けんかの舞」「仲直り三角の舞」「くじの舞」で構成されます。文明年間(1469~1487)頃より大森・鳥見神社の祭礼で舞われていたものが、延宝6年(1678)に平岡・鳥見神社に伝わったといわれています。
別所の獅子舞
別所の獅子舞は、約800年前、獅子頭をかぶり、囃子をつけて村内を巡り歩いて悪疫退散を祈願したものが、次第に猿楽や能楽などの要素が取り入れられ江戸時代初期あたりから現在の形態になったといわれています。
この舞は、笛師の囃子にのり、三匹の獅子(雄獅子・中獅子・女獅子)が舞うもので、「道笛」「讃仰の舞」「愛楽の舞」「鎮護の舞」「降伏の舞」で構成されています。
江戸時代は春・夏・秋の年三回行われていましたが、現在は8月23日に宝泉院で、翌24日に地蔵寺で演じられています。
いなざき獅子舞
いなざき獅子舞は秋分の日に和泉鳥見神社へ奉納されるもので、秋の豊作に対する感謝を表したものです。「いなざき」とは稲の収穫を前にしてという意味です。
大獅子、中獅子、女獅子の三匹獅子に道化が加わり、「道化の舞」「四方固めの舞」「花笠めぐりの舞」「綱くぐりの舞」が奉納されます。特に道化の舞の中での道化のしぐさは子孫繁栄を意味しています。
鳥見神社の神楽
毎年10月17日、鳥見神社例大祭に社前の神楽殿で演じられ、大和神楽または十二座神楽と呼ばれています。
演者は14人で、内容は「捧幣式」「かため巫女」「かため翁の神」「国かためくなどの神」「五穀祖神種薪」「千箭発弓」「海上めきょう楽」「神剣宝鏡」「榊笹行事」「天狐乱舞」「おのころ島起源」「出雲国しずめ」「山神悪鬼徐伏」「宮殿作行事」「天岩戸前事」「大神宮」からなり、神代の物語と郷土の農耕生活を反映したものとなっています。
文安年間(1444~1449)から始まったと伝えられ、現在使われている16の面の大半に宝暦元年(1751)作の銘が入っています。
浦部の神楽
浦部の神楽は、10月第3日曜の鳥見神社例大祭と7月最終日曜の阿夫利神社例大祭に神楽殿で12の演目が演じられる十二座神楽です。
内容は、「神子舞」「翁舞」「神明の舞」「鈿女の舞」「恵比寿舞」「鍛冶の舞」「榊葉の舞」「二匹天狐の舞」「玉取りの舞」「大蛇の舞」「天之岩戸の舞」「火男の舞(ぶっきり舞)」で構成されています。
江戸時代の初期、阿蘇村村上(現八千代市村上)から伝えられたとも旗本上杉家祈祷所として、鳥見神社を鎮座した際に江戸より求め伝えられたともいわれています。
YouTube
お問い合わせ
印西市役所教育委員会 教育部文化振興課文化財係
電話: 0476-33-4714
ファクス: 0476-42-0033
電話番号のかけ間違いにご注意ください!