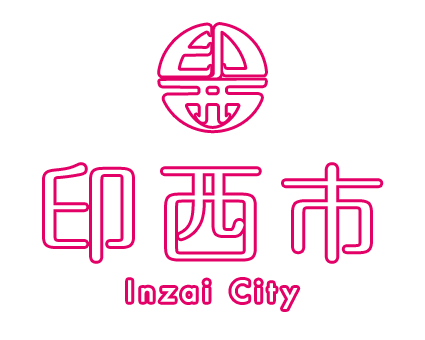[2025年6月10日]
ID:14365
医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が後から高額療養費として支給されます。(ただし入院時の食事代や保険の対象とならない差額ベッド料などは支給の対象外となります。)
また、保険証利用登録されたマイナンバーカードで受診するか、あらかじめ「限度額等が記載された資格確認書」の交付を受けることで、窓口負担額が高額になった場合に自己負担限度額までに抑えることができます。
千葉県後期高齢者医療広域連合」ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
自己負担限度額について
- 1か月(同一月)に医療機関等で支払った一部負担金の合計が自己負担限度額を超えた場合、申請すると高額療養費として自己負担限度額を超えた分の払戻しが受けられます。該当する方には、受診してから3,4か月後に通知を発送します。申請書を同封いたしますので、通知を受けてから申請してください。
(注意)対象者の一部負担金額(1~3割負担分)については、医療機関等からの診療報酬明細書(レセプト)で確認いたしますので、事前にお申し出いただく必要はありません。
- 医療機関等によるレセプトの提出は、一月毎に審査機関に提出されます。その後の審査(約1か月間)により適正と認められたものについて、高額療養費を算定しておりますので、通知発送までに時間がかかりますことを、ご了承ください。
- 75歳到達月については、誕生日前の医療保険制度(国民健康保険や健康保険組合など)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額を本来の限度額の2分の1に減額します(1日生まれの方を除く)。
| 負担割合 | 所得区分 | 外来(個人ごとに計算) | 外来+入院(世帯で合算) |
|---|---|---|---|
| 3割 | 現役並み[3] | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数回該当のとき140,100円)(注1) | |
| 現役並み[2] | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数回該当のとき93,000円)(注1) | ||
| 現役並み[1] | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数回該当のとき44,400円)(注1) | ||
| 2割 | 一般2 | 18,000円、または6,000円+(外来総医療費ー30,000円)×10%の低い方を適用(注2) (年間[8月~翌年7月]144,000円上限) | 57,600円(多数回該当のときは44,000円)(注1) |
| 1割 | 一般1 | 18,000円 (年間[8月から翌年7月]144,000円上限) | 57,600円 (多数回該当のときは44,400円)(注1) |
| 区分[2] | 8,000円 | 24,600円 | |
| 区分[1] | 15,000円 | ||
所得区分について
現役並み所得者3
市民税課税所得(課税標準額)が690万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者
現役並み所得者2
市民税課税所得(課税標準額)が380万円以上690万円未満の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者
現役並み所得者1
市民税課税所得(課税標準額)が145万円以上380万円未満の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者
一般2
市民税課税所得(課税標準額)が28万円以上145万円未満で、「年金収入+その他の合計所得」が被保険者が1人世帯の場合は200万円(被保険者が2人以上の世帯は320万円)以上の方
一般1
現役並み所得者、一般2 区分2、区分1以外の被保険者
区分2
世帯全員が市民税非課税の方
区分1
世帯の全員が市民税非課税で、その世帯全員の個々の所得(年金収入は、控除額80万円(注意1)として計算。また、給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除して計算)が0円となる方。市民税非課税世帯で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方
(注意1)令和7年度からは80.67万円となります。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について
(注意)お手元にある期限が有効な認定証は、住所や負担割合等に変更が生じない限り令和7年7月31日まで使用可能です。
【自己負担限度額表】の所得区分が「現役並み[1]・[2]」、「区分[1]・[2]」の方はマイナ保険証、または「限度額等が記載された資格確認書」を医療機関の窓口でを提示することにより、1か所の医療機関の窓口における月ごとの支払い額があらかじめ自己負担限度額までとなります。また、区分[1]・[2]の方は、入院時の食事代等も下記の通り減額されます。
医療機関において、医療費自己負担限度額の提示を求められた場合は、医療費自己負担限度額を記載した資格確認書を交付します。ご希望の場合はご申請ください。
「限度額等が記載された資格確認書」は申請いただくと、記載されている限度区分の発行期日から適用されます。
(注意)「現役並み3」および「一般1・2」の方は、限度額等に関する情報の提示は不要で、マイナ保険証または資格確認書(有効な保険証)の提示のみで窓口での支払額が自己負担限度額までとなります。
マイナ保険証利用の場合
医療機関での受付時にマイナ保険証を提示し、限度額情報の提供にご同意いただければ、支払いは限度額までとなります。
資格確認書(有効な保険証)利用の場合
| 申請要件 | 所得区分が「現役並み[1]・[2]」、「区分[1]・[2]」の方 |
|---|---|
| 申請に持参 するもの | ・本人の後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療資格確認書 ・代理の方の本人確認書類(マイナンバー、運転免許証など) ・委任状(代理人が親族以外の場合)または、登記事項証明書(代理人が後見人の場合) ・長期入院該当の申請をする方は、入院日数のわかる領収書など |
| 申請窓口 | (即日交付)国保年金課(本庁舎)、印旛支所、本埜支所 (申請のみ、後日郵送)駅前出張所 |
| 有効期間 | マイナ保険証、資格確認書と同じ |
入院した時の食事代
一食あたり下記の標準負担額を自己負担します。
(注意)区分2・1の人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、マイナ保険証をお持ちでない方は、上表「限度額等が記載された資格確認書」により申請をしてください。
療養病床以外の病床に入院するとき
| 所得区分 | 一食当たりの食費 |
|---|---|
| 現役並み所得者・一般(注意1) | 510円 |
| 区分2(90日までの入院) | 240円 |
| 区分2(過去12ヶ月で91日以上の長期該当) | 190円 |
| 区分1 | 110円 |
(注意1) 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は300円
療養病床に入院するとき
| 所得区分 | 一食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者・一般 | 510円(一部医療機関では470円) | 370円(注意1) |
| 区分2 | 240円 | 370円(注意1) |
| 区分1 | 140円 | 370円(注意1) |
| 老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 |
療養病床に入院しており、人工呼吸器・中心静脈栄養などを必要とする場合、難病などで入院医療の必要性が高い場合は、入院時食事療養費と同額に負担が軽減されます。
(注意1)特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は0円
お問い合わせ
印西市役所市民部国保年金課高齢者医療年金係
電話: 0476-33-4470
ファクス: 0476-42-8901
電話番号のかけ間違いにご注意ください!